オススメ記事
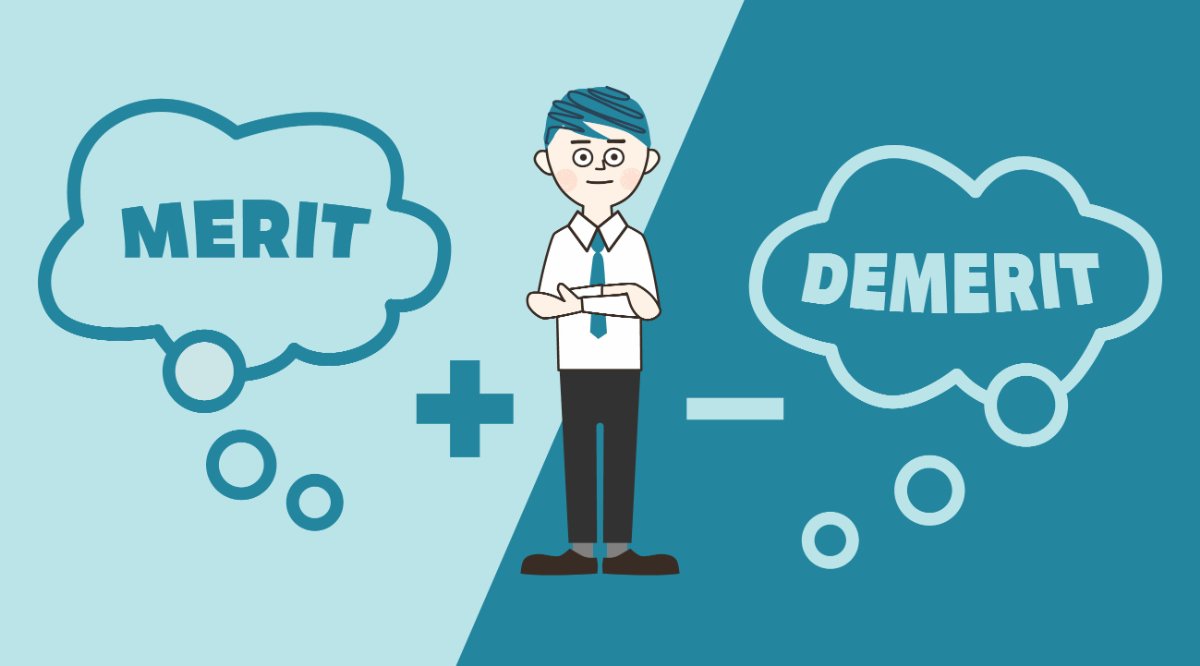
医師が個人事業主になるメリット・デメリット、法人化のほうが良い?
医師が開業をめざす場合、個人事業主として開業するのか、法人化するのか、悩む方も多いのではないでしょうか。 今回は、医師が個人事業主になるメリット・デメリット、法人化との違いについて解説します。

医療法人の開業手続きは、「各都道府県(市)」「法務局」「厚生局」など複数の窓口で行う必要があり、それぞれ提出期限も異なります。スムーズに開業するには、手続きの流れを把握したうえで、漏れのないように進めなければなりません。
そこで今回は、医療法人の開業手続きの流れを中心に、メリットやデメリットについても分かりやすく解説します。

医療法人とは、医療法の規定に基づき、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設の開設を目的として設立する法人のことです。
開業医として診療所などを開業する場合、個人で開業するのか、医療法人として開業するのか悩まれる方も多いのではないでしょうか。
現在、医療法人の開設に際しては、既に個人事業として病院、診療所等を開設し一定期間(最低数年程度)の運営実績が無いと、医療法人の設立は認められません。
個人経営と医療法人の最も大きな違いは、事業を行う人格です。
個人経営の場合は、開業者である医師が事業を行うため、契約や報酬は開業者個人に帰属します。
一方で、医療法人の場合は法人格として事業を行うため、契約や報酬は医療法人に帰属することになるのです。
個人経営と医療法人それぞれにメリットとデメリットがあるため、それぞれの違いを理解しておくことが大切です。
個人経営のクリニックと医療法人の違いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
https://iinshokei.biz/column/clinic-015.html
医療法人開業の手続きは、各都道府県によって提出書類等の細かい部分が異なります。
ここでは、医療法人開業のおおまかな流れについて解説します。
一つひとつ見ていきましょう。
医療法人の設立認可申請を行う際、都道府県によっては事前登録が必要であったり、説明会への参加が必要であったりするケースがあります。
これらが済んでいないと仮登録を行うこともできない場合があるので、注意が必要です。
医療法人設立認可申請は、以下のような手順で進めます。
設立認可申請書は各都道府県に提出します。設立認可申請書の審査と医療審議会による審議に通過すると、設立認可書が交付されます。
医療法人の設立認可書を受領したら、2週間以内に設立登記を行います。
医療法人の設立登記に必要な情報は、以下の通りです。
次に、診療所開設許可申請書または病院開設許可申請書を保健所に提出します。
事前に保健所と協議が必要な場合もあるので注意しましょう。
診療所開設許可申請書と同時に、診療所開設届も保健所に提出します。
保険診療を行うためには、保険医療機関指定申請の手続きが必要です。
地方厚生局へ保健医療機関指定申請書を提出しましょう。

医療法人を開業するメリットには、以下のようなことがあります。
個人経営の診療所の場合、開設できるのは1施設のみです。
しかし、医療法人であれば複数の開設ができるので、事業を拡大していくことも可能です。
個人経営の場合、病院・診療所以外の医療機関を開設することはできません。
医療法人であれば介護老人保健施設の開設もできるため、多角経営を行うことができます。
個人経営の場合、経営者の報酬は経費として認められていません。
しかし、医療法人の場合は役員報酬や給与として受け取ることができます。給与所得は経費として認められるため、節税効果が得られます。
個人経営の診療所を相続する場合、個人の預貯金や有価証券などの他に、医院の土地や建物、医療設備などが相続財産に含まれます。
そのため、相続税が高額になり、相続税の支払いが困難になってしまうケースもあります。
一方で、医療法人の場合は診療所の土地、建物、医療設備は個人の相続財産には含まれません。
そのため、将来、子どもなどに承継や相続する際の節税対策になります。
医療法人を開業するデメリットとしては、以下のようなことがあげられます。
今回紹介したように、医療法人の設立にはさまざまな書類を準備して計画を立て、漏れのないように手続きを進めなければなりません。
法人設立の手続きが煩雑で時間がかかる点は、医療法人を開業するデメリットの一つと言えます。
医療法人として診療所を開業する場合、個人経営では行う必要のない事務手続きが増えることになります。
事務手続きが煩雑な点も医療法人のデメリットと言えるでしょう。
医療法人の代表者となる理事長は、一般企業の代表者と同様に、社会保険や厚生年金の加入が必須になります。社会保険の手続きも必要となり、金銭的な負担も増えることになります。
医療法人の開業にはさまざまな手続きが必要になるため、説明会への参加から法人設立までには、少なくとも半年~12ヶ月ほどの期間が必要だと言われています。
医療法人の開業方法としては、新規開業後の法人成以外に事業承継による開業があります。
事業承継による開業の場合、ゼロからの設立ではないため、初期費用を大幅に抑えることができ、患者やスタッフ、医療機器のリース契約などもすべて引き継ぐことが可能です。
ただし、事業承継による医療法人開業の場合も、開業手続きは漏れなく行う必要があります。
医療法人にはいくつかの種類があり、持分ありの医療法人と持分なしの医療法人では手続きの内容が異なるため、実績のあるコンサルティング会社など、専門家の力を借りて行うのがおすすめです。

診療所の開業は、個人で開業する方法と医療法人として開業する方法があります。
医療法人として開業することで得られるメリットは多くありますが、開業の手続きは煩雑で時間もかかります。
医療法人の開業は、新規で開業するだけではなく事業承継によって開業することも可能です。
すでに開業している医療法人を引き継ぐことで、比較的スムーズな開業準備と手続きを進めることができるでしょう。
医療法人にはいくつかの種類があり、それぞれ必要な手続きが異なります。
名南M&Aでは、全国800件以上の医療機関の業務サポートで培ったグループノウハウと、医業専門チームが一丸となり医師のサポートを行っています。承継開業までの煩雑な手続きや交渉については担当アドバイザーが窓口となり、実績のある専門チームでバックアップいたします。
医療法人の開業や事業承継は、名南M&Aにぜひご相談ください。
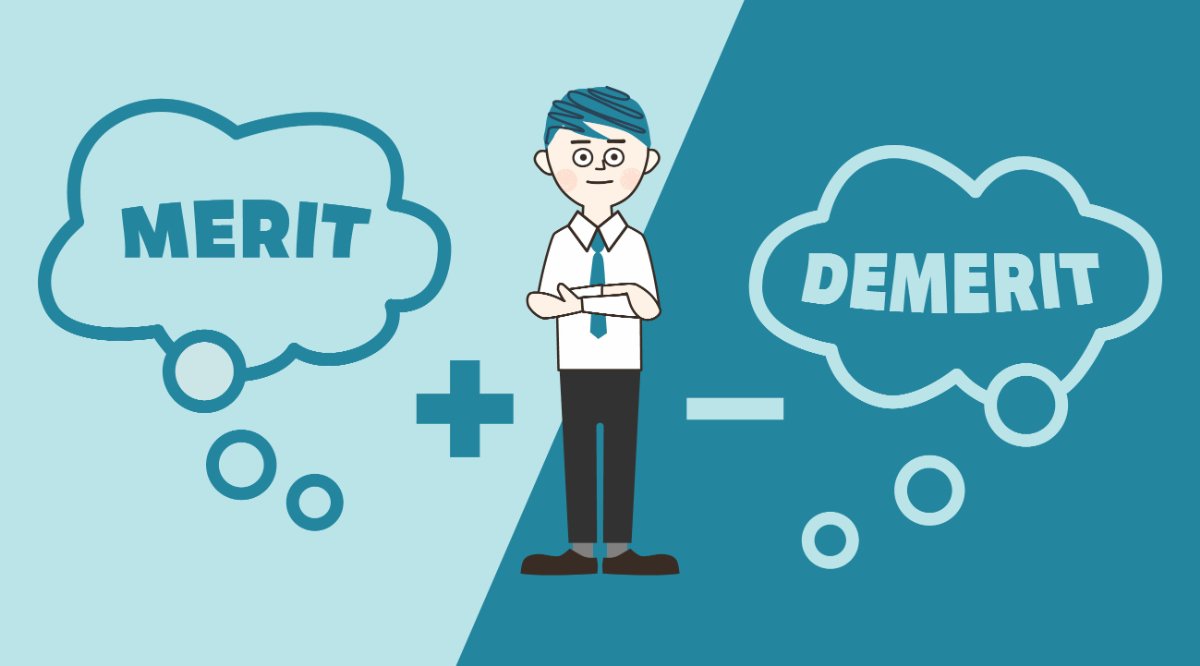
医師が開業をめざす場合、個人事業主として開業するのか、法人化するのか、悩む方も多いのではないでしょうか。 今回は、医師が個人事業主になるメリット・デメリット、法人化との違いについて解説します。